それ、ずっと引っかかってたんですよね──
『ユーベルブラット』って、最初は“剣と魔法の王道ファンタジー”だと思って観てたんですよ。
でも、話が進むにつれて、あの“七英雄”の扱いに…うっすら違和感、ありませんでした?
「なんか、キレイすぎるぞこの伝説」って──
そう思ったの、僕だけじゃなかったはず。
光に見えてたものの正体が“影”だったとき、人はどうするのか。
そして、それでもなお、その“光”を守る人々の中で、真実を剣に託した男の話。
今回はそんな、“語られなかった英雄譚”の裏側を、感情と構造の両面からほどいていきます。
嘘に彩られた“七英雄”の歴史

称賛されるべき存在が、もし“嘘”でできていたとしたら──?
物語の土台である“七英雄伝説”は、実はすべてがねじれていたんです。
信じていた英雄は、誰かの嘘でできていた
神託歴3968年。帝国は異邦への討伐のために14人の勇士を送り出します。
その中で3人は戦死。7人が任務を放棄して帰還し、
残された4人は使命を完遂しながらも、裏切り者として処刑された──
これ、完全に“正義のすり替え”なんですよね。
帰還した7人は、自分たちの保身と栄光のために、真の英雄たちを葬った。
にもかかわらず、帝国はその7人を“七英雄”として讃え、歴史に刻んでしまうわけです。
“正義”を語る者こそ、いちばん怪しかった
名誉も地位も武勲も、すべては嘘の上に積み重ねられていた──
なのに、それを誰も疑わない。
いや、むしろ疑うことすら“罪”になるような空気。
これ、現実でも時々見かける構造ですよね。
「みんなが信じてるから正しい」っていうムードの怖さ。
あの七英雄は、まさにその象徴だったんじゃないかと思うんです。
“名前”を取り戻すための旅路

真実を奪われ、名を奪われ、命さえ奪われた少年が、
20年後、“黒き剣”を携えて戻ってくる──
これ、ただの復讐じゃないんですよ。
彼にとっての戦いは、「なかったことにされた歴史」への異議申し立てであり、
“自分は確かに存在していた”という証を、もう一度この世界に刻む行為だったんです。
剣を握るたび、あの夜の痛みがよみがえる
アシェリートは、“裏切り者”というレッテルを貼られ、同胞に殺されかけた。
──けれど生き延びた。妖精の力で肉体を得て、ケインツェルとして再誕した彼は、
帝国の裏側でひとり、静かに爪を研いでいたわけです。
剣を握るたびに思い出すのは、仲間の叫び声、血の匂い、あの夜の光景──
復讐とは、感情だけじゃない。
“歴史”と“存在”を取り戻す、彼なりの手続きだったんですよね。
名前を奪われた男が、再び名を取り戻すまで
誰にも覚えられていない。
自分の名は呪いのように封じられ、語られることすら許されない──
その状態って、もはや“死”よりも深い孤独じゃないですか。
だから彼は、“ケインツェル”という仮の名で動きながらも、
その刃で少しずつ、自分の“本当の名前”を掘り起こしていく。
名を取り戻すって、記憶を取り戻すことでもあるし、
何より「自分が自分であってよかった」って確かめる行為でもある。
あの剣は、そういう意味で、“記憶を発掘するシャベル”だったのかもしれません。
それでも彼は、剣を抜くしかなかった

誰かに語ることすら許されなかった“真実”を、
言葉ではなく、“刃”で語るしかなかった少年の覚悟──
本当は、あんな方法じゃなくてもよかったのかもしれない。
でも、帝国の誰も耳を貸してくれなかった。
それどころか、名前を出しただけで処罰されるような空気ができあがっていた。
そうなったとき、あなたならどうしますか?
彼は、「誰にもわかってもらえないまま生きる」より、
「剣を抜いて、自分の真実を刻む」ことを選んだんです。
言葉では届かない真実を、刃に託して
帝国中が信じていた“七英雄神話”。
それを覆す言葉は、もはや届かない。
嘲笑されるか、弾圧されるか──そのどちらか。
だから彼は、証明するために戦った。
血で汚れても、憎まれても、それでも「そこにいた」と証明するために。
剣は、ただの復讐の手段じゃない。
この世界に残された、唯一の“声”だったんです。
秩序か、真実か──“守られた嘘”を壊すという決意
七英雄の嘘は、国をまとめる物語だった。
それを壊せば混乱が生まれることは、ケイン自身もわかっていたと思うんです。
でも、“間違った物語”の上に安心を築いて、
本当の英雄を見捨てていいのか?
その葛藤が、彼の行動のすべてに滲んでいた。
“壊すこと”は怖い。でも、壊さなきゃいけない嘘って、あるんですよね。
彼の剣はその覚悟の象徴でした。
嘘の中で生きていた彼らもまた、壊れていた

“七英雄”として讃えられた彼らは、すべてを手にしたように見えた。
けれど本当は、その栄光の裏で、それぞれが何かを失っていたんです。
裏切られたアシェリートが“語る手段”を探していたように、
裏切った彼らもまた、“黙る方法”でしか罪と向き合えなかった。
その沈黙の中に、僕はひどく人間くさい痛みを感じたんです。
石碑の沈黙は、“赦されない過去”を語っていた
たとえばグレン。
七英雄の一人として栄光を手にしながら、
彼は密かに、アシェリートたちを悼む石碑を建てていた。
謝罪の言葉もない。言い訳もしない。
ただそこにあるのは、誰も訪れないような場所にぽつんと立つ石。
でもそれが、彼の精一杯だったのかもしれない──
“許されたい”とも言えない者の、沈黙の祈り。
語られなかった“もう一つの英雄譚”
僕らが知っていたのは、“語られた側の歴史”だけだった。
でもその影には、語られることすら叶わなかった“英雄”たちがいた。
裏切った彼らが、何を抱えて、何に怯えていたのか。
それを丁寧に拾っていくと、復讐劇だと思っていた物語が、
急に“悲しい群像劇”に変わって見えてくるんです。
たぶんこの物語、敵と味方の線引きじゃなくて、
“語られなかった人々”をひとりずつ照らしていくような優しさがある。
僕はそこに、一番ぐっときました。
感情って、こんなに複雑でめんどくさい

最後まで観終わって、真実もわかったし、復讐の理由も理解できた。
…なのに、スッキリしない。どこか胸がつっかえる。
いやもう、あんなに戦ったんだから、
「よし、これで正義はなされた!」って拍手したかったはずなんですよ。
でも現実は、「これで…よかったのか?」って気持ちがじわじわ残る。
正しさが勝っても、心が追いつかないときがある
七英雄の嘘は暴かれた。
ケインツェルはその手で“真実”を世界に突きつけた。
でも、そのことで傷ついた人もいるし、混乱が起きたのも確かで。
だから、「正しいこと」が「心地よい結末」になるとは限らないんですよね。
正しさって、思ったよりもトゲがある。
この世界に“ただの悪役”なんて、いなかった
誰かが裏切った。誰かが剣を振るった。
だけど、その一人ひとりに事情があって、選択があった。
だから「こいつが悪い」で終わらせられない。
…こういうのって、感情の整理がほんと難しいんですよね。
好き・嫌いとか、良い・悪いじゃなくて、
「なんでこうなっちゃったんだろう」って静かに思うやつ。
たぶん僕たちが感じてるのは、“人の気持ちのめんどくささ”なんです。
でも、それこそがこの作品の良さなんだと思いますよ。
まとめ:偽りの光に抗った、ひとつの“語りなおし”
『ユーベルブラット』は、ただの復讐譚じゃない。
それは、“歴史の書き直し”であり、“名前を取り戻す物語”であり、
そして、“誰が物語を語るのか”を問いかける、静かな反抗でもありました。
ケインツェルが手にしたのは、剣というペン。
その刃は、嘘を暴くだけじゃない。
忘れられた声を拾い上げ、なかったことにされた真実を、もう一度世界に刻むための道具だったんです。
光を壊すことが、正しさになるときもある
偽りの光を壊すのは怖い。
だって、それが誰かの“信じたもの”だったから。
でも、それでもなお、その嘘が他人の尊厳を踏みにじっているなら。
「もうそれは、壊されるべき光なんだ」と、ケインは教えてくれた気がします。
語られなかった物語に、耳を澄ませたくなる
物語の最後、どこかで誰かが泣いていた気がする。
それはケインでも、七英雄でもなく、
たぶん、名もなき兵士だったり、置いていかれた家族だったり。
その声に耳を澄ますと、『ユーベルブラット』は急に身近に感じるんです。
ああ、これって、「自分の話かもしれない」って。
だからこそ、僕はこの作品を、「剣の物語」ではなく、「声を取り戻す物語」として受け取りたいと思っています。
あなたは、この剣の音に、どんな気持ちを重ねましたか?
シリーズ記事まとめ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

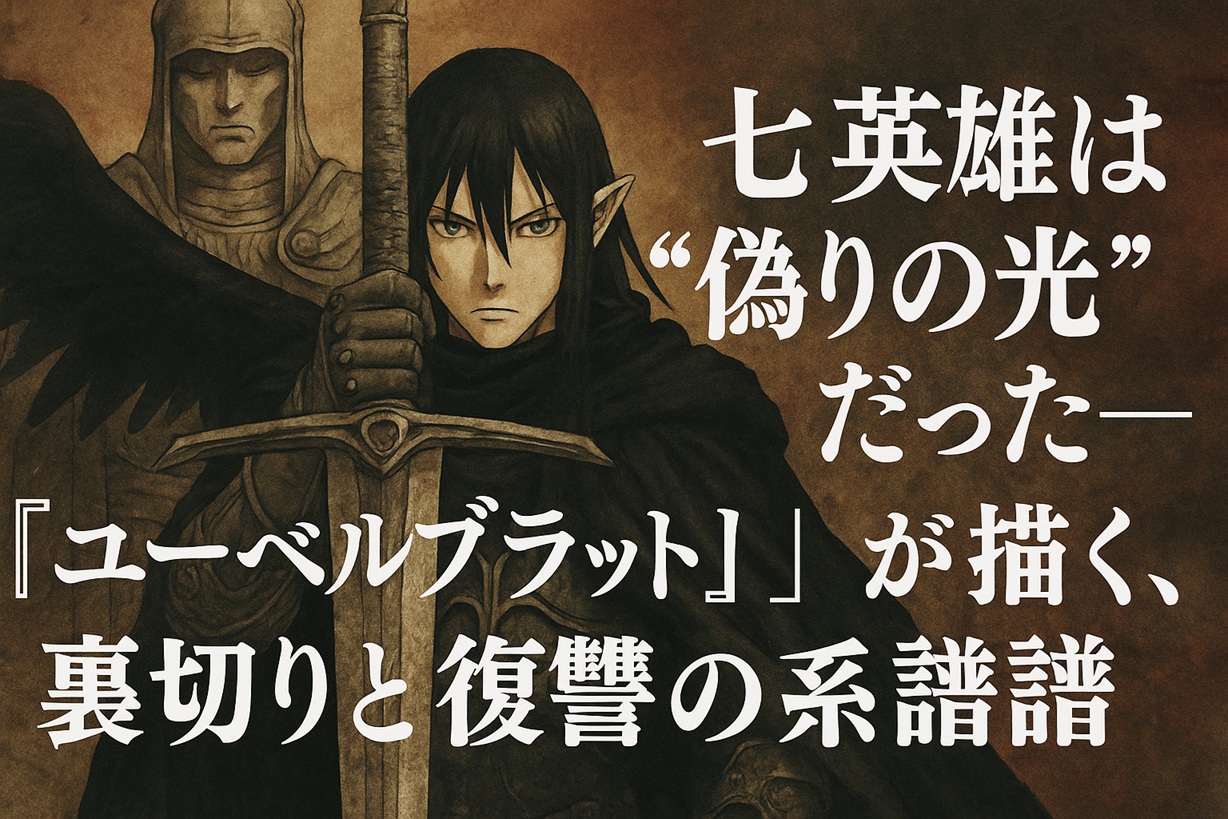


コメント