「アニメ化、楽しみにしてたんだけどな」
そんな声が、静かに、でも確かに届いていました。
『SAKAMOTO DAYS』――元・伝説の殺し屋が、平和な日常のなかで巻き起こすハチャメチャな戦い。
原作は、圧倒的なテンポと演出で読者を魅了してきた作品です。
だけど、2024年に放送されたアニメ第1部には、「ひどい」「がっかりした」という声も少なくありませんでした。
期待していた“あの迫力”が感じられなかった。
アクションのスピード感、原作のギャグセンス、キャラクターの魅力――
どこかうまく噛み合わないまま、静かに終わってしまった印象があったのです。
でも、それは“嫌いになった”ということじゃない。
むしろ、その違和感の正体にこそ、原作への「好き」の温度が詰まっているような気がしました。
この記事では、なぜ第1部が「ひどい」と言われたのかを、
作画・演出・テンポ・原作との違いという観点から構造的に掘り下げていきます。
そしてその先に待っている、第2クール(2025年7月14日〜)への「希望」についても触れていきます。
――たぶん、僕たちはもう一度、「サカモトデイズが好きだ」と思いたいだけなんです。
原作との“落差”――作画・アクション演出の違和感
アニメに期待していたのは、あの“原作の迫力”がそのまま映像になること。
でも実際には、「なんだか平坦」「動いているのに盛り上がらない」といった声が多く聞かれました。
とくに注目されたのは、作画とアクション演出の「熱量の差」。
一体、何が足りなかったのでしょうか──ここでは“原作の強さ”と“アニメでの再現性”の違いに焦点を当てていきます。
原作漫画は“止め絵”と“内側の動き”に強み
原作『サカモトデイズ』の魅力は、なんといっても「動きを感じる静止画」にあります。
ページをめくる手が止まらないスピード感、戦闘シーンの“呼吸”まで聞こえてきそうな構図の妙。
手描きのアクションが読者の想像力を刺激し、コマの間に“見えない動き”を生み出していたのです。
たとえば、坂本が一瞬で敵を沈める場面――
その“間”や“視線の流れ”を通して、読者の頭の中では自然と動画のように展開されていきます。
このような「読者に補完される動き」が、漫画というメディアの強みでもあります。
ところが、アニメではそれが必ずしも“そのまま動けばいい”というわけではありません。
期待した“動きの暴力”が描かれなかった…原作ファンの心象
「動けばもっとすごいだろうな」
そんな期待を持っていたファンにとって、アニメのアクションはどこか“おとなしい”ものでした。
とくに、構図が平面的でカメラワークに迫力がなく、
原作で感じていた“殺気”や“臨場感”が削がれてしまったという声が多く聞かれます。
動いているはずなのに、なぜか静止して見える――そんな逆説的な違和感があったのです。
「もっと“重さ”がほしかった」
「漫画の“ドン”ってくる感じが再現されてない」
原作のダイナミズムに惚れ込んでいた読者ほど、この落差は大きく感じられたはずです。
メディア転換の難しさと“動きを補う読者の内面補完”
アニメは“動くこと”が前提のメディアですが、だからこそ難しさもあります。
原作漫画では、コマの隙間を読者の想像力が埋めてくれますが、
アニメではそれをすべて「見せなければいけない」。
そのとき、“余白”をどう設計するかが、作品の手触りを大きく左右します。
つまり、ただ原作のコマを「なぞる」のではなく、
アニメとしての“新たなリズム”や“視線の誘導”が求められるわけです。
「原作どおりなのに、なぜか物足りない」
――それは、メディアが変わったことで、“補完される余白”が消えてしまったからかもしれません。
演出・テンポがくすむ瞬間
アニメは“時間の芸術”とも言われます。
テンポの緩急、カメラの「間」、台詞や沈黙のリズム──それらがすべて合わさって、感情の波が生まれる。
しかし『サカモトデイズ』第1部では、そうした演出の“間”がかすれ、
「なんとなく退屈」「原作より軽い」という印象につながってしまったのです。
ここでは、テンポと演出が“響かなかった”理由を、構造的に探ってみましょう。
カメラワークが単調で“間延び感”
まず、目立ったのが“止まりすぎるカメラ”です。
たとえば坂本の視線が動くシーン、敵との交錯、ギャグのオチ──
どれも「間」を演出するはずが、タイミングがズレたり、動きが少なすぎたりして、視聴者の集中が切れてしまう場面が散見されました。
これは、テンポをコントロールする演出の「タイム設計」がうまく働いていなかったことを示しています。
原作では読者が自分のリズムでページをめくれるのに対し、アニメではそのテンポを“作り手が決める”。
だからこそ、「一歩遅れる」演出は、物語の熱量そのものを鈍らせてしまうのです。
「あれ? もっとグッと来ると思ったのに…」
感情的に言えば、多くのファンはこう感じたはずです。
「アニメになれば、もっと迫力あるだろう」
「坂本の無表情ギャグが、声付きでさらに笑えるはず」
そう思っていたのに、届いてこなかった。
それは、演出の“溜め”が短く、ギャグやアクションの「ピーク」がぼやけていたからかもしれません。
原作で読者が自然に感じていたリズムが、アニメでは“ズレたまま”流れてしまった。
そのズレが積み重なることで、「なんとなく物足りない」という感情がじわじわと広がっていったのです。
視聴者の集中が途切れる瞬間と戻れないリズムの罠
演出テンポの崩れは、視聴者の“没入感”にも大きく関わります。
一度テンポが崩れると、どんなに後で盛り返しても、集中は戻りにくい。
とくに『サカモトデイズ』のような「一瞬の間」が命の作品では、それが致命的になってしまいます。
たとえるなら、リズムの悪い音楽を聴いているようなもの。
ずっと裏拍で進む演奏に、自然と身体が乗れなくなる──そんなズレが、演出面でも起きていたのです。
制作会社(トムス)のリソース限界とファンの焦り
作品の“完成度”は、必ずしもクリエイターの情熱だけで決まるわけではありません。
制作スケジュール、予算、スタッフの人数……アニメという現場は、見えない制約と常に闘っています。
『サカモトデイズ』のアニメ第1部が「物足りない」と言われた背景には、トムス・エンタテインメントの“体制的な限界”も見え隠れしていました。
ここでは、その制作事情と、ファンの“どうしようもない苛立ち”を丁寧にひもといていきます。
Dr.STONEとの同時進行、Netflix納品の影響
『サカモトデイズ』を制作したトムス・エンタテインメントは、同時期に『Dr.STONE』第3期の後半戦も手がけていました。
これだけでもリソースの分散は避けられません。さらに、Netflix向けのパッケージ納品方式が加わり、
1話ずつ修正・改善しながら放送する“空きスケジュール”がほとんどない状況だったと考えられます。
つまり、初期段階で詰めきれなかった絵コンテやレイアウトが、そのまま本編に反映されてしまう。
その結果として、「作画が省エネ」「動きが少ない」「演出に余白がない」といった印象が生まれてしまったのです。
「原作が好きだからこそ、足りない!と思ってしまう」
作品を“つまらない”と感じたとき、人はふつう離れていきます。
でも『サカモトデイズ』の場合は違いました。
「もっとよくできるはずなのに」「なんで、こうなったんだろう」
その不満の裏には、間違いなく“原作への愛”がありました。
だからこそ、ファンは苛立ちを覚えたのです。
好きなものが「本来の姿で伝わらない」ことへの、もどかしさ。
そして、制作の裏にある事情が見えれば見えるほど、「誰も責められない」という感情に、さらに自分自身が苦しくなってしまう──
制作構造を知ることで湧く共感と理解
この章で伝えたいのは、“誰かを責めたい”という話ではありません。
制作会社の事情、スケジュールの縛り、商業構造の複雑さ──
それらを知ることで、ファンの視線が「攻撃」から「共感」へと変わっていく瞬間があります。
たとえば、「次はもっと良くなってるといいな」
「限られた中でここまでやってくれたんだな」
そう思えるようになったとき、“ひどい”という評価は、ただの批判ではなく、
「もっと好きになりたいからこそ出た声」に変わっていくのだと思うのです。
評価は二極化――原作ファンと初見視聴者の温度差
「ひどい」と言う人もいれば、「普通に面白かったけど?」という人もいる。
アニメ『サカモトデイズ』第1部の評価をめぐっては、そんな“認識のズレ”がはっきりと見えてきます。
この章では、原作ファンとアニメ初見視聴者、それぞれの視点から見た“評価の分岐点”を掘り下げ、
なぜ感想がこれほどまでに分かれてしまったのかを考えてみます。
原作ファンは後悔・批判の声
SNSやレビューサイトを見ていると、もっとも厳しい声を上げているのはやはり「原作を読み込んでいたファン」でした。
「このシーン、なんでカットされたの?」
「坂本の重みがない」「シンが軽く見える」
「“静と暴力”のメリハリが弱い」
彼らの言葉には、裏切られたような寂しさと、愛する作品を“違う何か”として見せられたような不満が混ざっています。
とくに、原作の“手触り”を大切にしていたファンほど、アニメでその温度がズレていることに敏感だったようです。
初見視聴者の安心感、「テンポ遅めでも気にならなかった」
一方で、アニメから『サカモトデイズ』に触れた視聴者の反応はおおむね好意的でした。
「テンポはゆっくりだけど、キャラが好きになれた」
「ツッコミが面白い」「雰囲気がやさしくて観やすい」
「殺し屋って聞いてたけど、けっこうコメディ寄りで気楽に見れた」
これは裏を返せば、原作の“激しさ”を知らないぶん、アニメのマイルドな演出がちょうどよかったということでもあります。
つまり、“何を期待していたか”が、評価を大きく分ける要因になっていたのです。
比較があると苦しくなるのは自然な心理構造
僕たちは「好きなものが変わってしまうこと」に、とても敏感です。
それは恋人でも、日常でも、そして“物語”でも同じ。
「こうあるべきだ」「こう見えていてほしい」
そんな理想像が自分の中にあるからこそ、実際に出てきたものとのギャップに、傷ついてしまうんです。
でも、それって“好きだった証拠”なんですよね。
初見の人はただ「今ここにあるもの」を楽しめるけれど、ファンは「以前あったもの」と比べてしまう。
その心の構造を理解すれば、「評価が割れる理由」もきっと、少しだけ優しく見えるはずです。
「第2クール」で期待できる改善とは?
「なんだか別のアニメみたいだった」
そんな驚きの声が、2025年夏の放送前にすでに上がり始めています。
アニメ『サカモトデイズ』第2クールの予告映像が公開されると、SNSでは「作画クオリティが上がってる」「これは期待できそう」という声が急増。
第1部で抱いたモヤモヤは、“次こそ”という希望に変わりつつあります。
この章では、第2クールに込められた“巻き返しの兆し”を、具体的な改善点から見ていきます。
キャラ作画やアクション演出の向上が注目
まず目につくのが、キャラクター作画の精度向上です。
特にシンや南雲、ボイルといった人気キャラの線が“引き締まり”、表情のキレも格段にアップしている印象を受けます。
加えて、アクション演出も第1部に比べて動きが格段にダイナミックに。
PV映像のなかでは、手描きの格闘描写に“重み”が戻ってきており、戦闘のスピード感や「一撃の説得力」が感じられる構図が随所に見られました。
これは、前半で指摘された“間延び感”や“動きの平坦さ”に対する、明確な改善の意志と見てよさそうです。
「あれ…これ別アニメみたい!」第1部からの驚き
SNS上ではこんな感想が目立ちました。
「同じ作品?」「やっと本気出した?」
そんな言葉がポジティブな意味で飛び交っているのです。
特に印象的なのが、“光と影”の使い方の変化。
コントラストを強めた絵作りがシリアスさを増し、キャラ同士の緊張感がぐっと引き締まっています。
そのおかげで、ギャグとシリアスの落差にも“振れ幅”が出て、テンポにメリハリが戻ったように感じられるのです。
希望に寄せるファンの「今度こそ!」という熱量
第1部でモヤモヤを抱えてしまったファンも、「今度こそ」という気持ちを胸に、第2クールを待っているようです。
それは、諦められないから。
「もっと面白くなるはず」「あの原作のポテンシャルを、アニメでも見たい」
そんな願いが、いま再び高まり始めているのです。
変化の兆しが見えたとき、人はもう一度、信じてみたくなる。
そしてその“再び好きになりたい気持ち”こそが、物語とファンをつなぎ直す大切な糸なのだと思います。
まとめ──“ひどい”の奥にあった感情と、もう一度の期待
✔️なぜ第1部は「ひどい」と言われたのか?
-
原作にあったアクションの“迫力”や“構図の妙”が再現されず、作画と演出に物足りなさが残った
-
テンポや間の取り方が甘く、“緊張感”や“感情の起伏”が感じにくかった
-
制作会社のリソースやスケジュールに起因する“事情”も影響し、全体の仕上がりに影を落とした
それらの要因が重なり、ファンからは「期待していただけにショックだった」という声が集まりました。
✔️でも、“それでも好き”が残ったからこそ
「ひどい」と言うのは、もう二度と観たくないからではなく、
「もっと良くできるはず」「本来の面白さはこんなもんじゃない」──そんな“諦めきれない気持ち”の裏返しです。
初見の視聴者と原作ファンの温度差があったのも、
それぞれが「どこに価値を見ていたか」が違ったから。
それは決して優劣ではなく、「見ていた景色の違い」なのだと思います。
✔️第2クールは“再び信じる機会”になるかもしれない
予告映像ににじむ変化。作画の密度、アクションの迫力、キャラの表情に戻ってきた“鋭さ”。
そこには、たしかに“再挑戦”の気配があります。
もしあなたが、第1部で心が離れかけたとしても──
第2クールはもう一度、「好き」を取り戻すチャンスになるかもしれません。
記憶は薄れても、“好きだった気持ち”は、心のどこかに残っている。
そのかすかな熱を、もう一度信じてみても、きっといいはずです。
シリーズ記事まとめ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
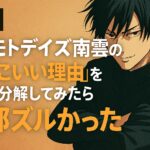



コメント